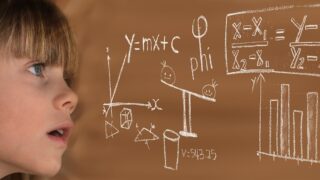一級建築士
一級建築士 【構造】地盤より。傾斜地盤について。切土した地盤により重い建築物を建築すると斜面の安定性はどうなる?そもそも切土ってどういう意味だっけ?
今回は傾斜地盤についてです。令和7年のNo.19の1枝に出題されたました。これまで出題されることはありませんでしたが、問題の文章からはイメージつかない方がいるのではないかと思いまして…(私はすぐにイメージできませんでした…)整理することにしました。問題を読んですぐに理解できた方もいらっしゃると思いますが確認ということでお付き合いください。