 一級建築士
一級建築士 【環境】温熱指標について。SET*(標準新有効温度)が25℃なら温冷感は「快適」?PMV、OT、MRT、WBGTってなんだっけ?重要テーマをわかりやすく解説!
本記事では、温熱指標とは何か、どんな種類があり、どのように出題されるのかを、初心者にもわかりやすく解説していきます。特に「指標ごとの違い」を押さえることが得点につながりますので、最後までぜひご覧ください。
 一級建築士
一級建築士  一級建築士
一級建築士 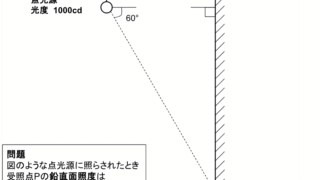 一級建築士
一級建築士  一級建築士
一級建築士  一級建築士
一級建築士  一級建築士
一級建築士  一級建築士
一級建築士  一級建築士
一級建築士  一級建築士
一級建築士